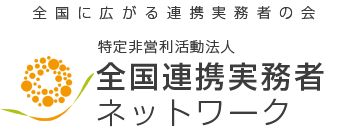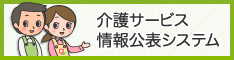退院が近づいたら…
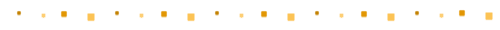
患者はこんな心配や不安を抱いています
- 退院後の生活が心配、誰に相談したらいい?
- 介護保険って聞いたことあるけど、どうしたらいい?
- ケアマネジャーってどうやって決めるの?
- 介護保険のサービスを受けたいんだけど・・・
- 車椅子や電動ベッドを使いたいんだけど・・・

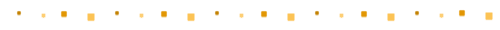
入院中の生活から、自宅での生活に変わるとき、患者には多くの不安があります。介護保険の利用やケアマネジャーの紹介など、相談に応じるのも地域連携室の役割です。
介護保険
最期まで健康でありたいと願っていても、高齢になると加齢による病気などにより、寝たきりや認知症などで、介護が必要になることもあります。
そんな高齢者の暮らしを社会みんなで支える仕組みが介護保険制度です。

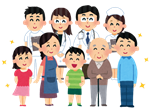
40歳以上の人は介護保険に加入し、保険料を支払います。その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要な人は費用の一部を負担するだけで、さまざまなサービスを受けることができます。
介護保険を利用することで、患者は退院後の生活をスムーズに開始できます。
介護保険の利用には申請が必要です
介護保険を利用する時は、市町村が行う「要介護認定」を受ける必要があります。「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。

申請に必要なもの
□ 申請書
□ 介護保険の保険証
(40~64歳の方は健康保険証)
その他市町村によって異なります
主治医から医学的な意見を求めます。本人の心身の状態をよく把握している医師に依頼しましょう。
認定調査
調査員(市職員など)が訪問して心身の状態などを聞き取り調査します。


※認定結果に納得ができないときは、都道府県の介護保険審査会に申し立てができます。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?
ケアマネジャーは、介護に関するコーディネートを行う人のための公的資格で、福祉や保健医療の分野で実務経験のある人が取得できます。
介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるように、本人やその家族からの相談に応じたり、関係機関への連絡・調整を行ったりします。
利用者は、介護認定の申請後に、担当のケアマネジャーを決定し、在宅で受ける介護サービス等の相談をします。
ケアマネジャーは、利用者の希望や利用限度額等に基づいてケアプラン(介護サービス計画)を作成し、最適な介護・支援が受けられるように総合的なコーディネートやマネジメントをします。

各市町村には、「地域包括支援センター」という介護に関する相談が受けられる場所も設置されています。
退院前訪問
退院前訪問とは、退院される患者が円滑に在宅生活を送っていけるよう、自宅に訪問し、家屋内外の段差・配置などの状況把握や、住宅改修の提案、福祉用具の活用、自宅での動作指導・生活指導等を行うことです。
入院中の担当理学療法士・作業療法士、看護師、ソーシャルワーカー等が訪問します。
退院後に担当するケアマネジャーや住宅改修事業者とともに訪問するとよいでしょう。訪問日時については、患者・家族と相談の上、決定します。

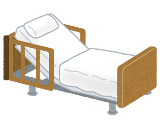
退院前多職種合同カンファレンス(退院前カンファレンス)
患者・家族が安心して退院し、自宅等で安定した療養生活ができるよう、入院中の病院スタッフと退院後の在宅医療・ケアスタッフが集まり、患者情報の伝達・共有を行います。
カンファレンスには患者・家族、ケアマネジャーにも参加していただきましょう。
患者の状態や治療方針を共有することにより、受入側の医療・ケアスタッフは、退院後の療養計画やケアプランを立てやすくなります。
患者・家族も、退院後のスタッフと顔を合わせ、在宅療養での希望等を伝えることにより、安心して退院に向けての準備に取り掛かることが出来ます。

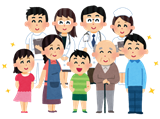
訪問看護
訪問看護とは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、訪問看護ステーション等の看護師が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供することで、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。

訪問看護サービスの内容
- 療養上のお世話
- 病状の観察
- 医療機器の管理
- ターミナルケア
- 床ずれ予防・処置
- 介護予防
- 在宅でのリハビリテーション
- 認知症ケア
- ご家族等への介護支援・相談等